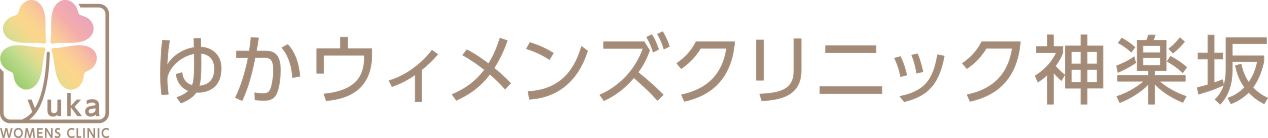- 6月 7, 2025
- 1月 2, 2026
NIPTを受ける前に知っておきたい!認証施設と非認証施設の違い
最近、NIPT(新型出生前検査)を希望する妊婦さんが増えています。
出生前に染色体の異常の可能性がわかるこの検査は、赤ちゃんやご家族の未来に関わる大切な検査です。
でも実は、どこで検査を受けるかによって、その後の対応やサポート体制が大きく変わることをご存じですか?
今回は、「認証施設」と「非認証施設(無認可施設)」の違いについて、できるだけわかりやすくお話したいと思います。
認証施設とは?
認証施設とは、厚生労働省の専門委員会が定めた基準を満たし、正式に認められた医療機関です。
ただ検査ができるだけではなく、妊婦さんが安心して検査を受け、結果を理解し、必要に応じた次のステップに進めるための体制が整えられています。
認証施設は、以下のような厳しい条件をクリアしています:
・医師がNIPTに関する十分な知識と経験を持っている
・検査前後に遺伝カウンセリングを行う体制がある
→ 検査でわかること/わからないこと、陽性・陰性・判定保留とは何か、陽性が出たときの流れ、限界やリスク(偽陽性・偽陰性など)を、ゆっくり時間をかけて理解できるまで説明します。妊婦さんとご家族が納得した上で検査を受けられることが大切にされています。
・検査結果は医師が対面で丁寧に説明
→ 「メールで通知されるだけ」ではなく、面談形式で結果を伝えます。医学的な説明にとどまらず、妊婦さんの気持ちに寄り添ったサポートが受けられるのも大きな特徴です。
・検査後の精密検査(羊水検査など)を確実に実施できる連携体制がある
→ 結果が「陽性」や「判定保留」となった場合、連携している基幹病院で羊水検査などの確定診断をスムーズに受けられます。つまり、“陽性が出た後にどうすればいいのか”を一人で悩むことはありません。
このように、「検査の質」「説明の質」「サポートの質」すべてにおいて、一定水準以上であることが保証されているのが認証施設です。
非認証施設(無認可施設)とは?
国の認証を受けていない医療機関や検査提供施設のことを、「非認証施設」または「無認可施設」と呼びます。
これらの施設でもNIPTを受けることは可能ですが、カウンセリング体制や検査後のサポートに大きな違いがあります。
たとえば…
・遺伝カウンセリングが行われないことが多く、偽陽性の可能性や検査の限界についての説明がない
・検査結果がメールや郵送で一方的に届き、対面での説明がない。相談もできない
・陽性と判定されても、確定診断を受けないまま中絶を選択してしまうリスクがある(実際には陰性=偽陽性だった場合も)
・羊水検査などの確定検査は自分で手配する必要がある
・3つのトリソミー(13・18・21)以外の異常を含む「検査項目が多いNIPT(より多くの異常を調べるNIPT)」を提供している施設もある
「検査項目が多いNIPT(より多くの異常を調べるNIPT)」とその注意点
非認証施設では、微小欠失症候群などを含むNIPTを提供していることがあります。
中には、本来のNIPTの目的から逸れ、検査項目を多く設定して差別化を図る動きも見られます。
最近では、産婦人科以外の診療科(皮膚科や内科など)でもNIPTを取り扱うケースが増加しており、妊婦健診や出生前医療に関する知識や経験が乏しいまま検査を提供している事例もあります。
その結果、医学的なサポートが行われないまま「検査だけが一人歩きしてしまう」ケースが報告されており、営利目的での導入が社会的にも問題視されています。
以下のような点にも注意が必要です:
・医学的に精度が十分に確立しているのは、トリソミー13・18・21の3つのみでそれ以外のトリソミーは、着床に至らないか、妊娠初期に自然流産となります。
・微小欠失症候群とは、染色体のごく一部がわずかに欠けている状態です
→ 欠けた部位によって症状の程度が大きく異なり、無症状の方もいれば、発達や行動に特徴が見られるお子さんもいます
・微小欠失の多くは、通常の羊水検査(Gバンド法)では診断できず、マイクロアレイ検査などの高度な遺伝子検査が必要です。
・出生前に異常が指摘されても、生まれてみないと影響があるかどうかは分からないため、判断には慎重さが求められます。
このような理由から、国際的な学会(例:アメリカの産婦人科学会など)でも、NIPTはトリソミー13・18・21の3つに限定すべきとされています。
日本の認証施設でも、この方針に従い、科学的根拠に基づいた検査のみを提供しています。
認証施設かどうかを見分けるには
NIPTを受ける際に、その施設が「認証施設」かどうかを確認することはとても重要です。
認証施設は、必ず「認証施設であること」を明記しており、厚生労働省の専門委員会(「NIPT等の出生前検査に関する専門委員会」)のロゴマークを掲示しています。
一方で、非認証施設は「非認可」や「無認可」などと書かれていることはほとんどなく、あたかも正規の施設のように見えることもあります。
見た目では判断しづらいため、利用前に公式サイトなどで「認証施設かどうか」を必ず確認することが大切です。
認証施設の一覧は出生前検査認証制度運営委員会(JAPCO)のホームページから確認できます。
最後に〜大切なのは“どこで”検査を受けるか
NIPTは、ただ「検査を受ければいい」というものではありません。
その結果をどう受け止め、どのように行動するかを含めて考える検査です。
だからこそ、どこで、誰と一緒に、どんなサポートを受けながら検査をするかがとても大切になります。
認証施設では、妊婦さんとご家族が安心して判断できるように、医師による丁寧なカウンセリング、結果説明、必要な検査への連携体制が整えられています。
一方で、非認証施設では検査の幅が広い分、正確性やその後のサポートが不十分なこともあり、必要以上に不安を抱えてしまうケースや、誤った判断につながってしまうリスクもあります。
赤ちゃんの命に関わる大切な検査だからこそ、医療の質とサポートが保証された場所で受けることを強くおすすめします。